
1.はじめに
●「夜中のトイレ介助が毎日続いて心配…」
●「親がギリギリまで我慢して、間に合わないことが増えてきた」
●「それでも本人は、おむつは絶対に嫌だと言う」
高齢のご家族を介護していると、排泄にまつわる悩みは避けて通れません。
年齢とともに体力やバランスが衰え、トイレまでの移動が難しくなる一方で、「自分で行きたい」「おむつは使いたくない」という気持ちは根強く残っています。
私は作業療法士として総合病院に18年間勤務し、多くのご家庭での排泄の困りごとに向き合ってきました。
その中でわかったのは、少しの工夫と補助具の活用で、尊厳を守りながら自立を続けられる方がたくさんいるということです。
この記事では、ポータブルトイレ、尿瓶、トイレ環境の整え方について、専門的な視点からわかりやすくご紹介します。
「自分らしい排泄」を支えるヒントを、きっと見つけていただけるはずです。
2. 自宅で使える排泄補助具とその特徴

高齢になると、身体の衰えによって「トイレに行く」という動作そのものが大きな負担になることがあります。
それでも多くの方が、「自分でトイレに行きたい」「できるだけ人の手を借りずに排泄したい」と思っています。
そんな方の尊厳や自立を支える道具として、「排泄補助具」はとても重要な存在です。
ここでは、ご自宅で活用しやすい3つの補助具をご紹介します。
1. ポータブルトイレ|トイレまで行けないときの“もうひとつの選択肢
ポータブルトイレは、ベッドや布団の近くに設置できる簡易トイレです。
夜間や体調がすぐれないときなど、「トイレまでの移動が不安」という方の強い味方になります。
特におすすめなのは、“夜間だけ使う”という選択肢です。
日中はトイレへ行き、夜間だけポータブルトイレを使うことで、生活のリズムや本人の自立心を保ちながら、安全も確保できます。
ポータブルトイレの活用チェックリスト
| チェック項目 | 該当する場合は要検討 |
|---|---|
| トイレまでの距離が長い | □ |
| 夜間の移動が不安・転倒経験がある | □ |
| トイレに間に合わず失禁してしまうことがある | □ |
| ベッドからの立ち上がりが大変 | □ |
| 家族の介助が必要で、夜間対応が難しい | □ |
これらに当てはまる方は、ポータブルトイレの導入を前向きに検討してみてください。
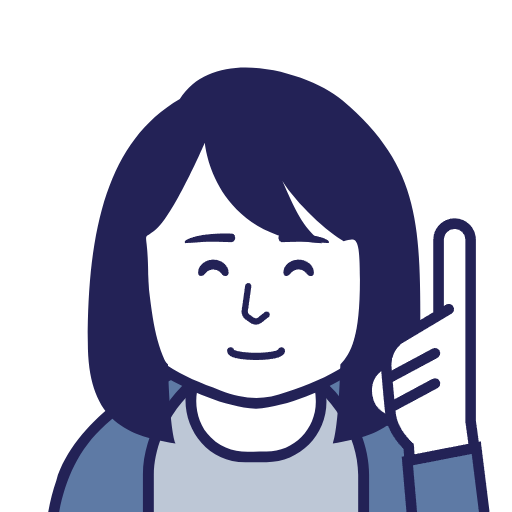
時間を決めて使用することで、生活のリズムや本人の自立心を保ちながら、安全も確保できます。
使用上の注意点
ポータブルトイレは便利な一方で、使い終わった後の処理がとても大切です。
誰が、いつ、どのように片付けるかをあらかじめ家族で話しあうことが、トラブルや不衛生を防ぐカギになります。
ポータブルトイレを選ぶときのポイント
| 視点 | 選ぶ際のチェックポイント |
| □サイズと設置場所の確保 | □ベッド脇に無理なく置けるか? |
| □手入れのしやすさ | □バケツの大きさや重さ |
2. 尿器(しびん)|寝たまま排尿ができる補助具
尿瓶は、身体を起こすのが難しい方でも寝たままで排尿できる器具です。
一時的な体調不良時や、夜間のトイレ回数が多い方、起き上ががり・立ち上がりに不安のある方に適しています。
多くは男性用ですが、女性用もあります。
使い慣れるまでに少し時間がかかることもありますが、「排泄は人に見られたくない」と思っている場合に、尊厳を保ちやすい道具でもあります。
尿瓶が役立つケースの一例
| 状況 | 尿瓶の有用性 |
|---|---|
| □立ち上がるとふらつく | ◎ ベッドで安全に排尿できる |
| □夜間のトイレ回数が多い | ◎ 起こす必要がないため介助者の負担軽減にも |
| □一時的に動けない状態(入院後、体調不良時など) | ◎ トイレまで行く必要がない |
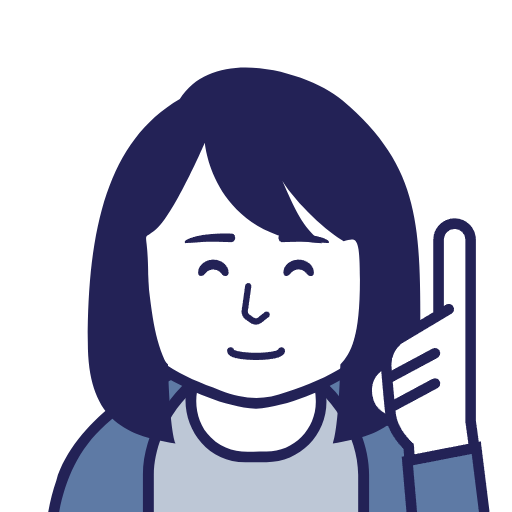
尿量が多い方は、破棄の頻度も多くなります。
3. トイレ内の環境調整|「いつもの場所」を安全に使い続けるために
排泄のための補助具も有効ですが、やはり「自宅のトイレで用を足せること」が最も望ましい状態です。
そのためには、トイレという場所そのものを使いやすく、安全に整えることが欠かせません。
トイレ内の改善ポイントと工夫
| 改善ポイント | 工夫・設置内容 |
|---|---|
| ●立ち座り動作 | 壁や便器周囲にL字型の手すりを設置する |
| ●便座の高さ | 高すぎず低すぎず、足が床につく高さに調整(高座便座を使用することも) |
| ●照明 | 夜間でも足元が見えるよう、足元灯や人感センサー付きライトを設置 |
| ●床材 | すべりにくいマットに変更する/段差をなくす |
| ●動線 | トイレまでの道に障害物を置かない/段差を解消する |
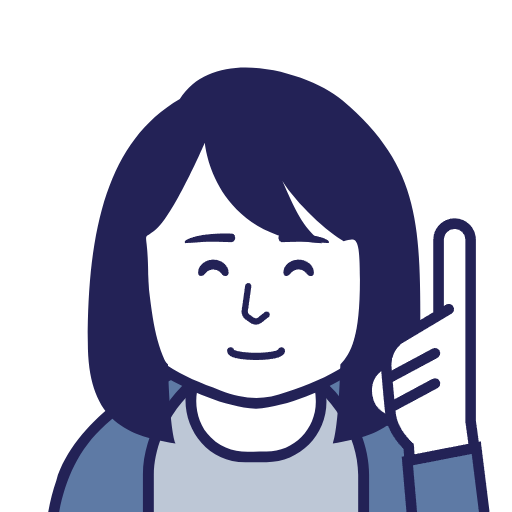
重要なのは、「高齢者本人の身体の状態」に合わせて調整することです。
市販の手すりや便座補高具、介護保険を使った住宅改修など、状況に応じて専門家の助言も受けましょう。
≫家族のために知っておきたい!介護保険を利用した家屋改修の基礎知識
4. 家族ができるサポートとは?
排泄のサポートは、身体的にも心理的にもデリケートなケアです。
そのため、ご本人だけでなく、ご家族にとっても大きなテーマになります。
まず大切なのは、ご本人の「自分でできることは自分でしたい」という思いを尊重することです。
排泄は人の尊厳にかかわる行為ですので、介助する側がよかれと思ってすべてやってしまうと、かえって本人の自信を損なってしまうこともあります。
一方で、体調や状況によってはどうしてもサポートが必要な場面も出てきます。
そんなときは、「家族が全部抱え込む」必要はありません。
ご家族へのアドバイス
- 無理をしないこと。できる範囲でのサポートを心がけましょう。
- ”完璧を目指さない”こと。日によって体調も気持ちも変わるのが普通です。
- 「何を手伝ってほしいか」を本人とよく話し合うことで、双方の納得感が得られます。
- 困ったときは、専門職(ケアマネージャー・作業療法士など)に相談することも大切です。
- 処理や見守りが必要な場合は、”「誰が」「いつ」「どこまでやるか」”を家族内で決めておくとスムーズです。
サポートの分担や話し合いのチェックリスト
| 話し合っておきたいこと | チェック |
|---|---|
| 夜間のトイレやポータブルトイレの使用の有無 | □ |
| 処理(洗浄・片付け)を誰が、どのタイミングで行うか | □ |
| 本人が嫌がること・不快に感じることは何か | □ |
| 家族が負担に感じていることは何か | □ |
| 外部のサポート(ヘルパー・訪問リハなど)の利用可能性 | □ |
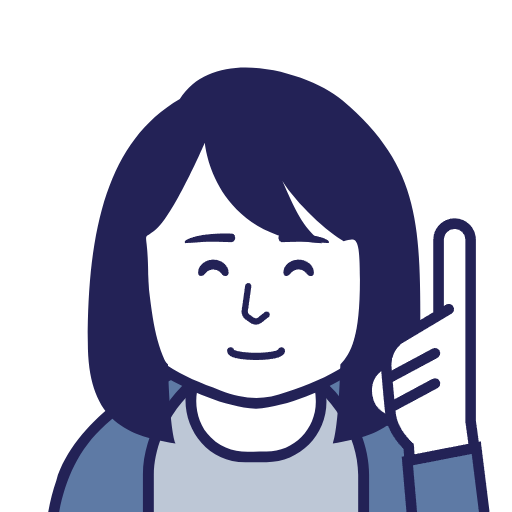
家族だけで頑張ろうとすると、疲れやストレスがたまり、関係がギクシャクしてしまうこともあります。
「お互いに無理をしないこと」「本人とよく話すこと」「助けを借りること」は、どれも恥ずかしいことではなく、安心して暮らしを続けるための大切な一歩です。
5. アドバイス
排泄に関する困りごとはとてもプライベートな話題です。
ご本人も話しにくく、ご家族も「どこまで踏み込んでいいのか」と悩むことが多いのが現実です。
そんなとき、私たち専門家が関わることで、本人の気持ちを大切にしながら、暮らしやすい排泄環境を一緒に考えることができます。
① ご本人に伝えにくいことを「代弁」できます
「そろそろポータブルトイレ使ってみたら?」
「おむつを考えた方がいいんじゃない?」
——ご家族にとっては切実な提案でも、直接伝えると関係が悪くなってしまうこともあります。
ケアマネージャーや私たち作業療法士などの専門職は、医療や福祉の知識を持ち、第三者として客観的にお話を聞き、必要な提案を“本人に寄り添った形で”お伝えすることができます。
本人も「専門家が言うなら…」と素直に受け入れやすくなることがあります。
② トイレ内の環境設定も専門です
専門職はは、「その人の身体機能」と「住まいの環境」を見極め、安全で使いやすいトイレ空間を整えるアドバイスができます。
たとえば、
●足腰の状態に合わせて最適な便座の高さを提案する。
●立ち座り動作を安定させるための手すりの設置位置を決める。
●トイレへの移動導線を安全にする家具配置や照明の工夫をする。
実際にご自宅に伺って、生活動作の様子を確認しながら提案できるのが専門職の強みです。
③ ご家族の介護方法もサポートします
排泄介助にはコツがあります。
たとえば、力任せではなく、相手の動きをうまく引き出すように動くことで、ご家族の負担がぐっと軽くなります。
また、こんな工夫も役立ちます。
●「声かけのタイミング」や「気づかせ方」を変えるだけで自発的な動作を引き出せる。
●無理に急がせず、本人のペースを尊重する介助の仕方
●ご家族の不安や疑問に、一緒に考えながら寄り添うサポートを行う
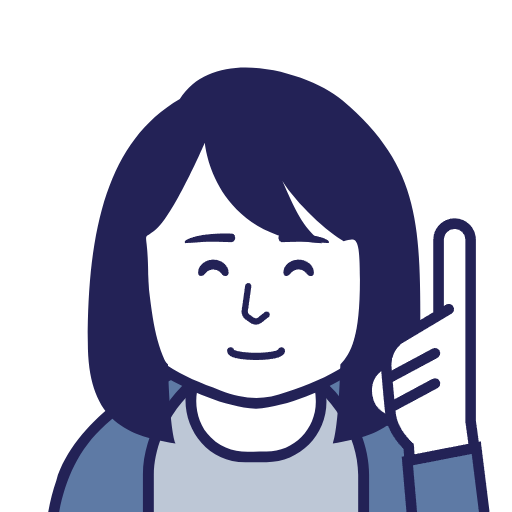
入院中や訪問リハビリなどでは、介助姿勢や動き方の具体的な練習も可能です。
「頑張りすぎない介護」「自分たちに合ったやり方」を見つけるお手伝いをするのも、専門家の大切な役割です。
まとめ
排泄は、人の尊厳や生活の質に大きく関わる大切な行為です。
年齢や体の変化に合わせて、ポータブルトイレや尿瓶、トイレ内の環境調整といった工夫を取り入れることで、安全に自立した排泄が可能になります。
ご家族は無理のない範囲で支え、必要に応じて専門職の力を借りることも大切です。安心して続けられる排泄環境を一緒に整えていきましょう。